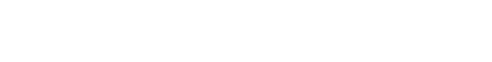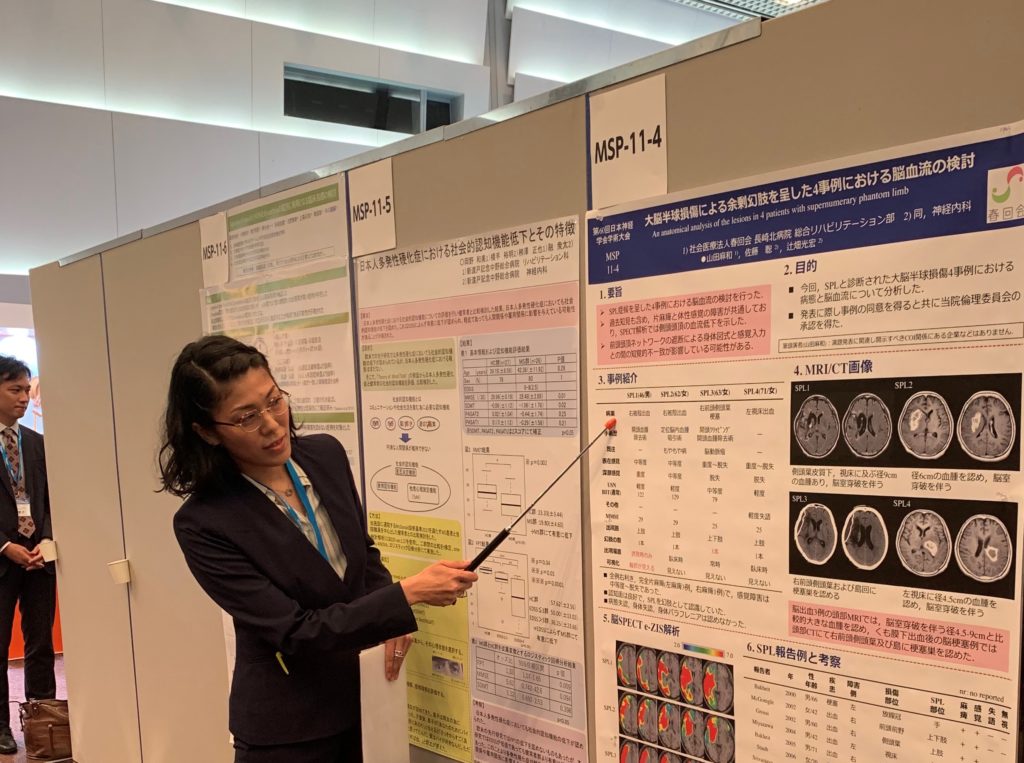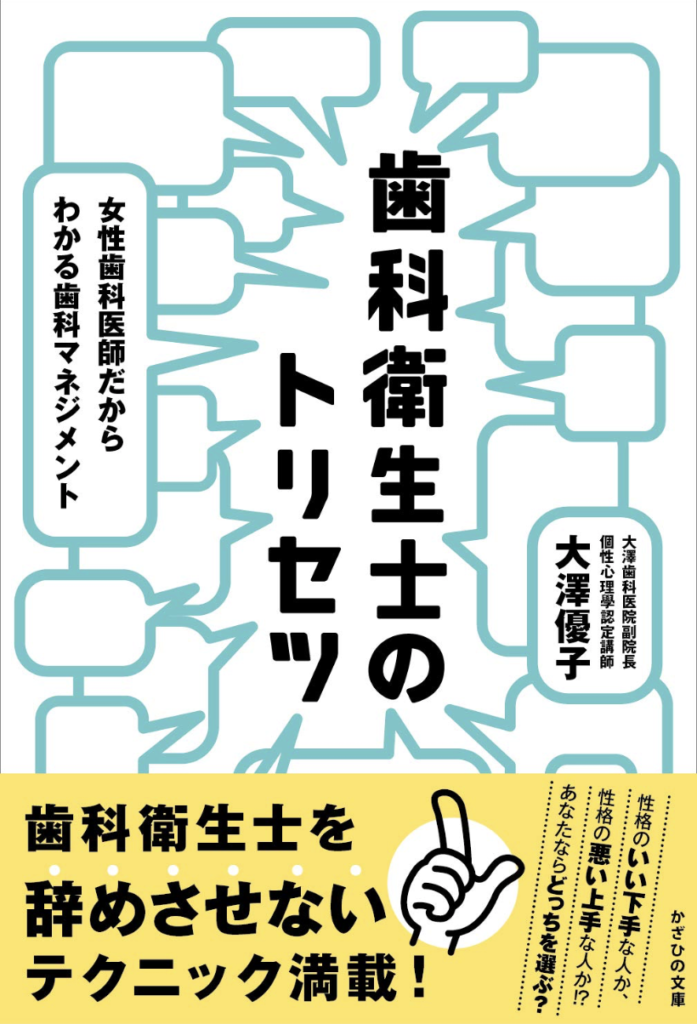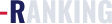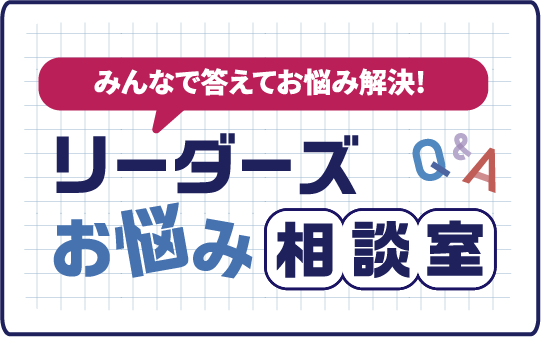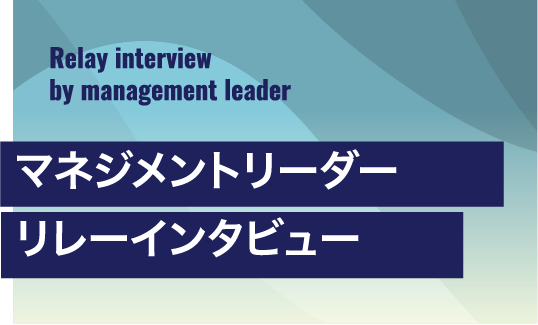群馬県玉村町にある医療法人樹心会角田病院のリハビリテーション部部長兼診療技術部長の富田隆之さんにインタビューしました。
角田病院は、前橋市、高崎市、伊勢崎市のベッドタウンである玉村町にある唯一の総合病院で地域医療の重要な役割を担っている病院です。
そこで活躍される富田さんは、若くして管理職となりリハビリテーション部を引っ張ってこられました。そのマネジメントをいろんな視点から伺いました。
*:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*
◎富田さんの所属の病院はこちら
医療法人樹心会角田病院
◎富田さんのプロフィール
平成19年 医療法人樹心会 角田病院
平成23年 同病院リハビリテーション科 係長
平成25年 同病院リハビリテーション科 課長
平成29年 同病院リハビリテーション部 部長 老健たまむら事務部長
令和 2年 同病院リハビリテーション部 部長 診療技術部 部長
・認定理学療法士(管理運営)
・群馬県理学療法士協会代議員
・理学療法士養成校 非常勤講師

◎現在の所属、役割やお立場をお教えいただけますか。これまでのご経歴もお願いいたします。
役割でいうと、2020年6月からは診療技術部長として薬剤や栄養、放射線科の多職種に携わっています。当院はリハビリテーション部が別にありますので、そちらの部長も兼務しています。
リハビリテーション部は現在、PTが57名、OTが20名、STが6名、そして歯科衛生士が1名とリハ助手が1名という構成になっています。
◎所属の病院、法人のご紹介(地域での役割、機能、特長など何でもPRしてください)をお願いいたします。
当院は、近隣の急性期病院から紹介された患者さんが、回復期や慢性期病棟へ転院されてきます。隣にある当院グループの老人保健施設や社会福祉法人ともつながりがあり、外来で体調が悪かった方が当院の急性期病棟へ来られることもありますし、回復期リハから直接、老人保健施設や社会福祉法人の特別養護老人ホームへ行くこともあります。
急性期から慢性期を診ており、それらにリハビリテーションが関わっているので、部としての力はだんだんと強くなってきています。
◎理学療法士になられた動機、きっかけを教えてください。
私は理学療法士になる前に、大学の経営学部を出ているのですが、そのあとに理学療法士の専門学校に進学しました。
大学で就職活動をしようとした頃は自分のやりたいことがわからなかったことがあります。私の性格的な部分として介護の世界でやっていくことがよいのではないかと考えました。そうして最初は介護福祉士を目指そうと思ったのですが、たまたま、理学療法士という職があると教えられて、近くのクリニックを訪れたところ、そこにいる理学療法士がとても輝いてカッコよく見えたので、この仕事をやってみたいと思ったのがきっかけです。
当時は、理学療法という言葉自体知りませんでしたので、学校に入ってから色々と学びを深めているうちに、勉強も楽しくなり、はまっていきましたね。そして、徐々に、理学療法士になる決意が出てきました。今では、天職だと思っています。
◎臨床の現場とマネジメントはどのように両立されているのでしょうか。
法人が運営している介護老人保健施設の事務長をしていたことがあるのですが、その時も外来のリハビリだけは続けていました。しかし、事務長の仕事がどんどん忙しくなって、それもできなくなってしまいました。
現在は病院に異動して、今でも新人の指導は行っています。臨床ではないのですが、それに近いことをやろうと心がけており、離れているようで離れていないという感じです。
やはり現場が好きですね。
この立場になってよく思うのが、上に立つと現場を見なくなる人が多いということです。私は現場へ足を運び、そこでスタッフと話をすることで情報を集めるようにしています。患者さんとも話をしますので、そういった意味では、リハビリテーションを直接、提供するわけではありませんが、病院全体を見ながらリハビリテーションに間接的に関わっているのだと思います。
◎現在、リハビリテーション部のまとめ役としてご活躍されているとのこと、PT,OT,STの3職種をまとめるコツや気を付けていることなどあればお教えください。
組織的にしていかないといけないですよね。PTとOT、STのトップそれぞれに役割をつけることかなと思います。当院の場合は、課長がPT、係長がOTとSTが担っていて、その中でも一つの職種が強くならないようにバランスに気をつけています。
また、それぞれ特徴があるので、例えばOTやSTがこういう風に取り組んでいくという方向性が出た場合、それを最終的に取りまとめるのが私の役割だと思っています。ただし、PTとしての視点で見るのではなく、リハビリテーション全体として見るようにしています。偏ってしまってはいけないので、その辺りは結構、意識しています。
◎リーダー(役職)になりたてのとき、壁にぶつかったこと、それをどのように克服したのかをお教えください。
私が2、3年目の頃に回復期リハビリテーション病棟が立ち上がったのですが、その時、リーダーとして上がほとんどいない状態で物事を進めていました。
結構苦労しました。他職種から色々言われましたしね。そのとき感じたことは、他の職種に理解してもらうためには、他の職種が我々のことをどう思っているのかを聞くことが大事だと思いました。当時は、他職種は自分より年上が多かったですし、職種のヒエラルキーがあります。その中でやっていくためには、人の話を聞いて、理解をした上でマネジメントする方向に持っていく能力が重要だと感じています。
私がトップとして6年目の頃に役職者が5人ほど一気に辞めました。その時に自分がこれまでやってきたリーダーシップというのは、「言うことを聞かせる」というトップダウンのマネジメントで、人の話を聞いてこなかったことに気づきました。そうすると皆、ついてこなくなりますし信頼関係も生まれないので、組織としては崩壊してしまいますよね。
◎リーダーとして、これだけは身に着けておいたほうがよい、経験しておいた方がよいと思うことをお教えください。
本をたくさん読むようにしています。ドラッガーの「人を動かす」もそうですし、人に伝える説明の仕方や方法を読み、そこで自分のやり方は完全に間違っていたと理解し、まずは人の話を聞くようにしました。
そうすることで何となく、うまくいくようになり、人がついてきたので、聞き上手になると言うことは大事なのかなと思っています。
◎これからのビジョンについてお聞かせください。
幸いにも今、病院の診療技術部長も兼務しており、栄養科や薬剤、検査など広くリハビリテーションに関わる分野を見させていただいています。やはり、リハビリ職はリハビリ自体には強いのですが、その他の部分には弱いという人が多いと思います。栄養とリハビリテーションは結構関わりがあるので、横のつながりをもっと強くしていくことでコラボレーションできる部分が出てくるのではないかと考えています。どうしても病院は、縦割りが強くなりますが、そこを横につなげられるような連携を私の立場でできればと思います。これが出来上がるとリハビリテーション部に入ったスタッフたちも広い知識が得られ、質が上がってきますよね。
また、病院や老健も含め、継続的に患者さんをみて状態が悪くなってしまったらまたすぐに戻すという環境、システムを作ることができたらとも思っています。
今は、新人のスタッフも入職してから3、4年目で他の回復期へ異動させるなど、できるだけ色々な経験をさせるようにしています。一つの部署だとマンネリ化して勉強しなくなってしまいますので。異動は悪いイメージがついてまわりますが、よいように捉えて欲しいですよね。
◎自分を元気にしたいとき、どんなことをされていますか。
今は子どもと遊ぶことですね。休みの日は、ほとんど子どもと過ごしています。
また、たまに時間をもらって日帰り温泉に一人で行くこともありますが、子どもを連れて行くことがあり、やはり子どもと一緒にいることが一番幸せを感じますね。

◎次世代のリーダーへアドバイスをお願いします。
今のリハビリテーションの業界は、上の人が抜けてきて若い世代が増えてきていますが、マネジメントとしては課題がたくさんあると私自身も感じています。
もっと苦労をしたほうがいいのかもしれません。よく言われることですが、若い頃に苦労しないと、その後あまり成長していかないですよね。昔は本当に苦しかったのですが、それが今はありがとうと思えるようになりました。例え、嫌なことがあったとしても続けていくことが10年後、20年後の自分の力になっていくのではないでしょうか。
そして、逃げずに目の前のことに自分の目で見ることがとても大事です。私も検査のことはわからないのですが、実際に見に行って質問しながら理解をしているという感じです。リハビリテーションの現場でも問題が起こることがあると思いますが、その時に自分で足を運んで目で見て解決に導いていく。現場重視だと思うので、そういった形で取り組みながら頑張っていただけたらと思います。
*:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*
【インタビュー後記】
法人全体のマネジメントに携わってこられた富田さん。リハビリテーション部の組織づくりから新病棟立ち上げ、様々な役割や職位でマネジメントの実務を着々と積み重ねてこそ身に着いたこと、気づかれたことがよくわかりました。
インタビュー中も、色々とご苦労をしてきたことが伝わってくる一方で、そこから得た自信を感じる場面もありました。
富田さん、インタビューのお時間をいただきありがとうございました!
-1.jpg)